はじめに

「考えるとは何か?」
普段、自然と行っているはずの行為なのに、改めて問われると答えるのが難しいテーマです。
自分自身、この問いに惹かれて手に取ったのが、今回紹介する
『はじめて考えるときのように 「わかる」ための哲学的道案内』(野矢茂樹さん 著、植田真さん 絵)です。
難解な専門書ではなく、やさしい言葉と挿絵で「考えること」の本質に触れられる一冊です。
読んでみて自分の思考習慣を振り返り、言葉の重要さを再確認できました。
ここでは、その体験をレビューとしてまとめたいと思います。
こんな人におすすめ

- とりあえず哲学の本を1冊読んでみたい
- 読みやすい本で「考える」ことを学びたい
- 世界観のある挿絵や雰囲気を楽しみたい
文章はひらがなが多く、ページ数も少なめなので、読書が苦手な人でも手に取りやすい構成です。
また、植田真さんの絵が本全体にちりばめられており、独特の世界に入り込んでいく感覚があります。
問いかけるような文体も特徴で、まるで著者と1対1で会話しているかのようです。
「考える」を考える

この本は「考えるとは何か?」を真正面から扱います。
考えることについて普段深く意識することは無いと思います。
しかし「どうやって考えたらいいの?」と聞かれても、すぐに答えるのは難しいですよね。
野球のバットの振り方のように「こうすればいい」とは教えられないし、ロダンの『考える人』のポーズを真似しても、それが考えることそのものを意味するわけではありません。
考えるという行為は、もっと自由で生活のあらゆる場面に入り込んでいます。
夜寝る前、入浴中、歩いている最中など、ふとした瞬間に「考える」ことは起こります。
考えるの多くは無意識に行われている

自分自身の体験としても、「考える」は意識して行うよりも頭の片隅で勝手に進んでいる感覚があります。
たとえば全然関係ないことをしているときに、急に「そうか!」とひらめく瞬間があります。
なぜそのタイミングで思いついたのか説明できない。
そうした無意識の働きが「考える」には大きく関わっています。
この本を読んで、その「無意識の思考」に改めて気づかされました。
考えるためには言葉が必要
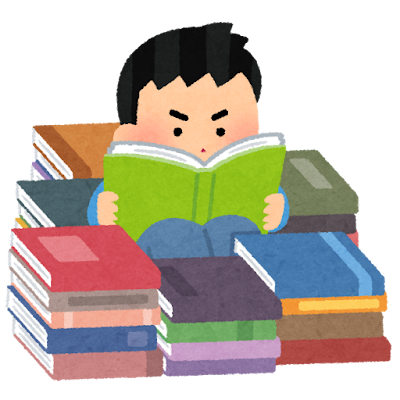
著者が強調しているのが「考えるためには言葉が必要」という点です。
いくら良いアイデアを思いついても、それを言葉にできなければ他者に伝えることはできません。
また、自分の頭の中でも、言葉がなければ思考は曖昧なまま流れてしまいます。
本を通して「語彙を増やすこと=考える力を鍛えること」というメッセージを受け取りました。
自分も「だからこそもっと本を読んで、言葉を蓄えていこう」と思えました。
まとめ

『はじめて考えるときのように 「わかる」ための哲学的道案内』は、哲学の入門書でありながら堅苦しさはなく、むしろ読者に寄り添うように「考えることの本質」を導いてくれる一冊でした。
読んでいるうちに、自分自身の思考習慣や言葉との向き合い方を振り返ることができます。
難解な哲学書に抵抗がある方でも、安心して読み進められる内容です。
「考えるって何だろう?」と少しでも立ち止まったことがある方に、ぜひおすすめしたい本です。
最後までお読みいただきありがとうございました!
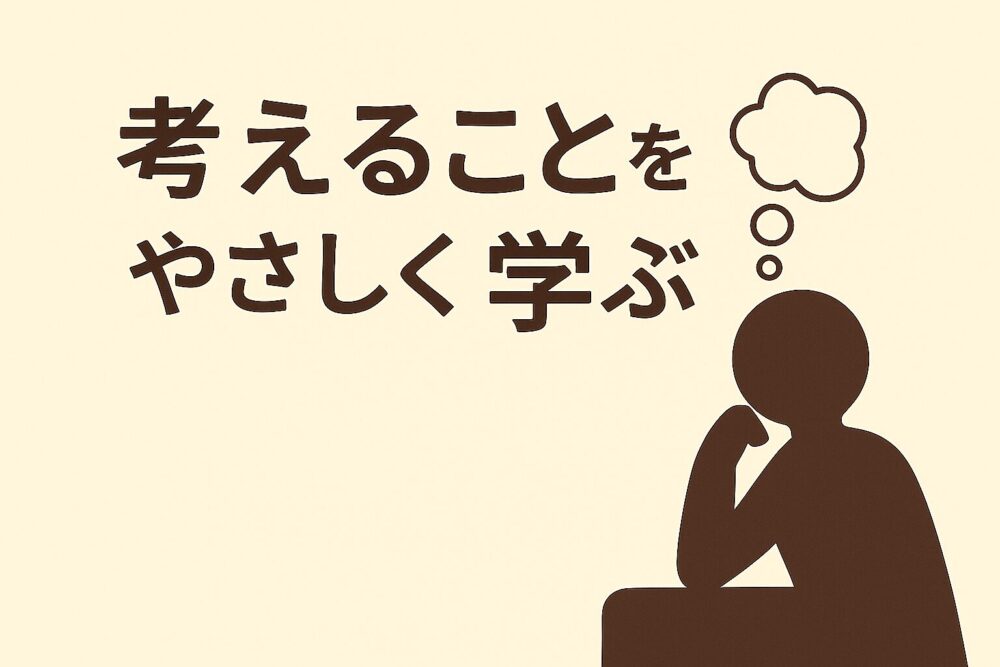
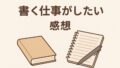

コメント