今回紹介する本は、北村紗衣さん著『批評の教室 チョウのように読み、ハチのように書く』です。
サブタイトルは、ボクサーのモハメド・アリの名言「蝶のように舞い、蜂のように刺す」に由来しています。
タイトルからも分かるように、この本は“批評”の方法を学べる一冊です。
自分自身、本や映画を観て「面白い!」と感じたときに、なぜそう感じたのかをうまく言葉にできずモヤモヤすることが多くありました。
評価されている作品に対しても「なぜ高く評価されているのか」が分からず、考えてしまうことも。
そんな悩みを解決してくれるのではないかと思い、この本を手に取りました。
切り口を一つにする大切さ
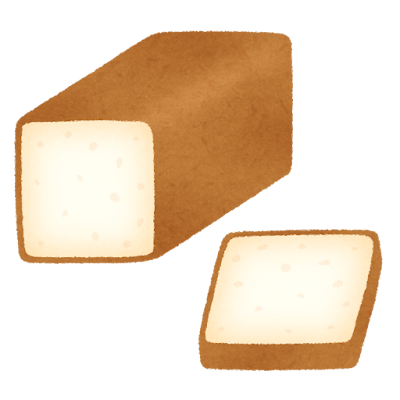
本書で学んだのは「批評には切り口を一つ決めることが大切」ということです。
私も読書感想ブログを書くにあたって「どうすれば書きやすいか」を調べたことがあります。
そのときに知ったのが「全体を漠然と書くより、部分的に焦点を当てた方が内容が濃くなる」ということ。
以来、心に残った部分や感銘を受けた箇所に印をつけ、感想を書くときにそこを中心にまとめるようにしています。
今回の記事も「ここについて書こう」と決めてから取り組みました。
これは本書の考え方と通じる部分があり、非常に参考になりました。
作品が何を表現しているのかに注目する
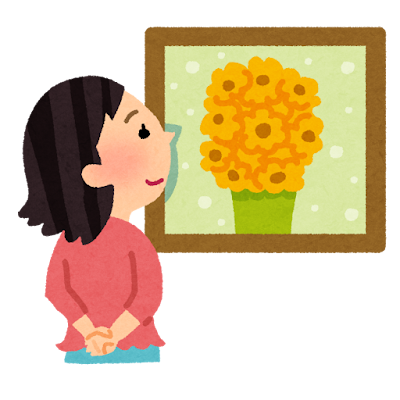
小説や映画には、基本的に「伝えたいメッセージ」が込められています。
例えばジブリ映画『千と千尋の神隠し』は、コミュニケーションについてのテーマがあるとよく言われます。
しかし、必ずしも全ての作品でメッセージが明確とは限りません。
そうしたときは作者から離れて「作品そのものが何を表現しているのか」に目を向けると良いそうです。
その方が自由に解釈でき、批評の幅も広がります。
批評には一つの正解があるわけではなく、多様な視点があっていいという考え方も印象的でした。
もちろん、攻撃的すぎる批判や過度に否定的なものは望ましくありません。
ですが、作品を深く読み解き自分なりに言葉にすること自体が“創造の第一歩”になると北村さんは書いています。
批評を書くことは自分を鍛えること

批評を書くことで責任も生じますが、それは自分にとっての学びでもあります。
本書を読んで、自分も「勇気を持って言葉にすること」の大切さを再確認しました。
このブログも、ただの感想にとどまらず、読む人に「なるほど」と思ってもらえるような批評記事を書いていきたいと思います。
批評に興味がある方や、自分の感じたことをもっと言葉にしたいと思う方におすすめの一冊です。ぜひ読んでみてください!
最後までお読みいただきありがとうございました。
感想やコメントをいただけると嬉しいです!
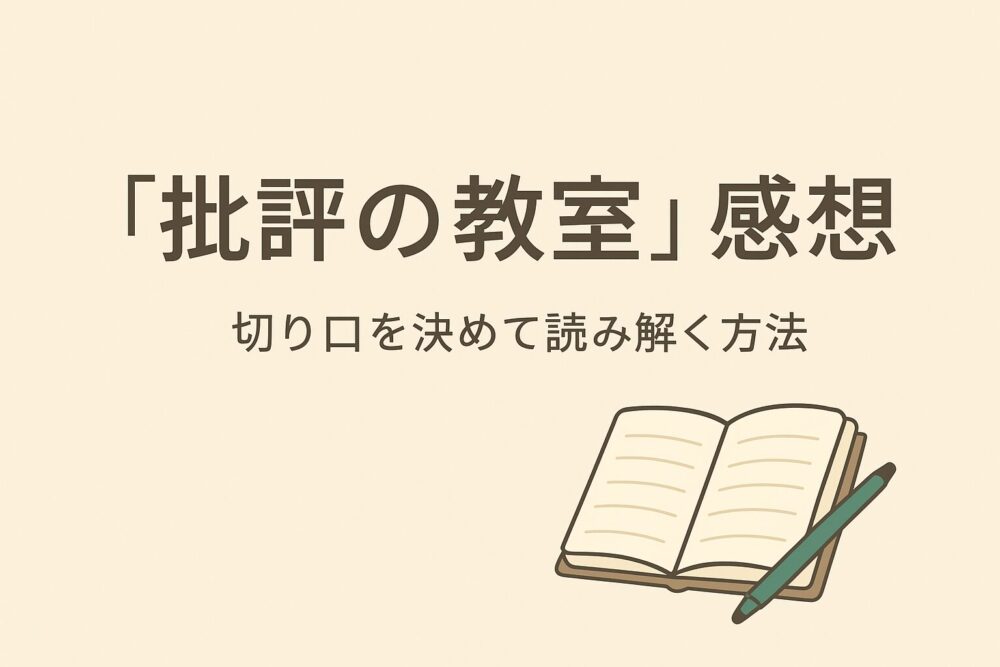
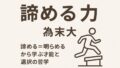

コメント